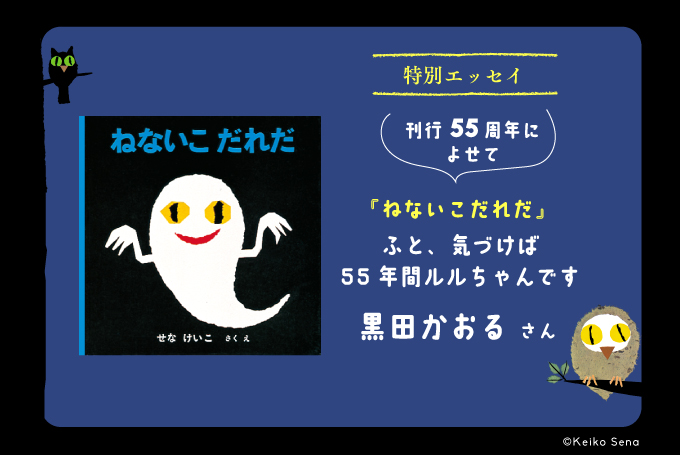特別エッセイ|田中琢治さん「くまのパディントン」シリーズ

「くまのパディントン」シリーズの翻訳者・松岡享子さんに続編の翻訳を催促の手紙を出した小学生がいました。その小学生は後に成長し松岡さんと共に「くまのパディントン」シリーズの訳者になったのでした。そんな田中琢治さんが『パディントン街へ行く』の刊行当時、広報誌「あのね」に寄せたエッセイを再掲します。
にくめないヤツ パディントン
田中琢治
読者の皆さん、初めまして。『パディントン街へ行く』から共同翻訳者に加えていただいた田中琢治です。訳者紹介を読んで、「はぁ、農学博士? 酵素? 学者さんがいったいなんでパディントン?」と思われた方も多いかと思います。 私が育った家の中には本があふれ返っていました。父も母も折にふれては、まだ小さくて字の読めない私に本を読んで聞かせてくれたことを覚えています。絵本から古典までいろいろです。自分で読めるようになってからは、お小遣いとは別に、本なら何冊でも買ってもらえ、母に連れられ図書館にも通いました。今風にいうと両親流の情操教育だったのでしょう。
そんな私が小学校1年のときのクリスマスに買ってもらったのが、『くまのパディントン』です。いまでもその本を持ってますが、ぼろぼろ。本当に繰り返し、繰り返し読んだのです。それがきっかけで松岡享子さんとの交流が始まり、詳しいことは後日に譲りますが、私にしてみれば「ヒョウタンからクマ(!)」のいきさつで、『パディントン街へ行く』の翻訳に携わらせていただきました。 今回、パディントンの9冊目『パディントンのラストダンス』を訳するにあたって、シリーズの既刊をもう1度読んでみました。『くまのパディントン』の初版は1967年10月1日ですから、今回の『ラストダンス』はちょうど40年目に刊行されることになります。時を経た今でも版を重ねているこのシリーズですが、なぜこのクマは世代を超えて愛され続けているのでしょうか?
もちろんパディントンというクマは、読者を楽しい気分にさせてくれ、魅力的です。しかし、よく考えてみれば、なにかと騒動を巻き起こす、実は「トラブルメーカー」のクマ。それがパディントンです。同じような早とちりで失敗を繰り返すパディントンと、そうなることが分かりそうなものなのにパディントンの好きにさせてしまっているまわりの人たち。正直にいえば、実際に自分の横にパディントンがいたら、ふつうなら気のいい人でも「もう結構」になると思います。今回、全部を読み返してみて、私は、まわりにいる人たちの魅力がパディントンの失敗を「憎めない」ものに変えているのだとあらためて気がつきました。
おおらかでちょっと鈍感なところのあるブラウンさん夫妻、子供の目線をもつジョナサンとジュディの兄妹、厳しくても心の底からパディントンが好きな家政婦のバードさん、機転のきく親友グルーバーさん、そして何度痛いめにあってもこりないカリーさん。パディントンがとんだことをしでかしても、何となくうまくおさまってしまうのは、このパディントンを見守る人たちのキャラクターによるところが多いと思います。
40年の間に日本の社会も変わり、人と人の関係もずいぶん変わったように思います。暖かく人を思い、ユーモアを持って、いつも楽天的におおらかに暮らしている、パディントンとそれを巡る人たちの魅力をゆっくりと味わっていただければ訳者としても、さらに子供の頃からの愛読者としても幸いです。
田中琢治(たなか・たくじ)
1962年、大阪で生まれる。7歳のときに両親からもらった『くまのパディントン』に夢中になる。京都大学で農学博士号を取得後、カナダに移住。現在サスカチュワン大学助教授。ペプチドに関連する酵素の研究が専門。
2025.04.02